月別アーカイブ: 7月 2014
舞台でアガらないために①
セミナーに参加してきました!
発表会やコンクール、グレード試験など、
人前で演奏する機会はけっこう多いもの。
「絶対にまちがえたくない」「今日だけは失敗できない」
と思えば思うほど、緊張はピークに達してしまい、
目はうつろ、指先は氷のように冷たくなり、
心臓バクバク、脚はガクガク、からだは宙に浮いちゃって…
その結果、ふだんの半分の力も出せなくなってしまいがちです。
どうしたら、アガらなくなるのか。
これは永遠のテーマです。
今回の講師は、武蔵野音楽大学の大場ゆかり先生。
もともとは、スポーツ選手のメンタルトレーニングを
受け持っておられたとのこと。
確かに、考えてみればスポーツの世界も同じですね。
大会本番で いかに平常心を保ち、いつもの実力・成績を
発揮できるか。それに尽きるのです。
しかし、大場先生曰く「緊張して当たり前です」。
あぁ、じゃあ、どうすればいいんですかぁ…(;´Д`)
「それはね、イメージトレーニングなんですよ」
なるほど…
ということで、次回をお楽しみに!(^^)
「おいらは鳥刺し」聴き比べ!
大人も子どもも一緒に楽しめる、
奇想天外なファンタジー作品。
以前、このオペラの中の人気のアリア(独唱歌曲)、
<夜の女王のアリア>にスポットを当てて紹介したことが
ありますが、今日はそれに勝るとも劣らない人気の
「おいらは鳥刺し」というアリアの聴き比べです!(^^)
<鳥刺し>ということば、気になりませんか?
鳥を刺す?なんや、それ。焼き鳥?
そう思う方は多いでしょう。
<鳥刺し>とは、鳥類の捕獲を仕事にしている人のこと。
「魔笛」の中では、夜の女王に鳥たちを献上している
<鳥おとこ>として、ユーモラスに登場します。
(ちなみに、教室の発表会でも「魔笛」の物語を上演したことが
何回かありますが、この曲は親しみやすく、みんなすぐに
おぼえてルンルンと歌ってくれました!)
まずは、ヘルマン・プライ。
そして、サイモン・キーンリーサイド。
なんと、ボカロの日本語バージョンまでありましたよ!(^^;)
(You Tube本当に便利…)
バイエル
みんな、有名なピアノの教則本です。
ふだんのレッスンでは、
「今日はブルクミュラーから弾こ」とか、
「チェルニーのあそこ、よく練習できた?」
などと、なにげなく口にしています。
だけど、よく考えればこれはみんな人の苗字。
ブルクミュラーという人が作った教則本であり、
チェルニーという人が作った教則本という意味なのです。
もし日本の苗字にあてはめたら、
「はい、松本の36番ひらいて」…と、いう感じでしょうか。(^^;)
バイエル(1806年の今日、7月25日誕生!)は、日本ではおそらく一番有名でしょう。
ところが、この人の伝記的なものは 現在ほとんど残されていません。
どんな人だったか、どんな生活をしていたか、全くわかっていないのです。
ピアノという楽器がだんだん改良されて一般に普及するようになり、
当時 先生と生徒もドッと増えたんでしょうね。
いちからピアノを指導するときに、優れたテキストが必要になりました。
バイエルさんは、一生懸命にこのテキストを作ったのだと思います。
今日では、タイトルもなく ときに単調に感じられる曲調が、
ともすれば敬遠されがちなバイエル教則本ですが、大人の方が
はじめてピアノを始める場合などは、とても使いやすく
練習しやすいテキストだと思います。
偉大な芸術作品を生むのも才能。
良い教則本を作るのも、また才能。
私たちには、どちらもありがたいことですよね!(^^)
楽器はとにかく続けること
載っているのを見つけました。
<…楽器というものは不思議なもので、ある程度
までは上達しても、それ以上の壁がなかなか乗り
越えられない。いわゆるスランプとなる。
しかし、その状態でも飽きずに続けていると、
あれ?と驚くように、ある日突然出来るようになる。
そうして、またもうひとつ高い壁に突き当たるの繰り返しである。>
(松浦弥太郎 「暮らしの手帖」編集長)
まさしくその通り…と思いながら読んでいると、その後が。
忙しくて、愛用のギターを弾けない状態がずっと続いたとのこと。
一年後に久しぶりに弾いてみたら、以前弾けていた曲がひとつも
弾けなくなっていて愕然とした。 そういう話でした。
また振り出しに戻ったけれど、今はリハビリをするごとく
出来たことを思い出すよう練習に取り組んでいるそうです。
松浦さんのエッセイは、
<継続は力なりとは本当である。週に一度でも、覚えた趣味は細々と
続けるべきだと痛感している。>
このようにしめくくられていました。
日々これ、鍛錬。
コツコツ地道にやっていくしかありませんよね!
でも、それが楽しいと思えることも大切。
焦らず、あわてず、楽器はとにかく続けていくこと。
それがいつしか大きな実りとなっていくのですから。(^_-)-☆
歌はなんて楽しい♡
鍵盤楽器とずっといっしょでした。
「音楽=鍵盤」みたいな人生だったんです。
ところが。
仲間うちで作っているバンドで、ひょんなこと
からvocalを担当することになって、気がつけば6年が経ってしまい…
これが、めちゃくちゃ楽しいんです!(≧▽≦)
腹式呼吸は健康に良いし、思いっきりシャウトすれば、
心のモヤモヤも たちまちスッキリ。
おまけに、体ひとつでどこでも音楽できる身軽さがこたえられない。
「これ、ホンマによろしいなぁ」って、練習のたびに大声出してます。(^^;)
Artとの出会いは人生を変える
姜 尚中さんの本を衝動買いしてしまいました。
ファンだったこともありますが、
タイトルに惹かれました。
『生と死についてわたしが思うこと』。
その中で、印象に残った一節があったので、
少し紹介します。
<わたしたちは3.11で生と死の近さを知りました。(中略)
非常に重たいテーマで昔なら宗教に向かったでしょうが、今は
必ずしもそうはいかない。たぶん、美術館は神なき時代の教会、
日本でいうと神なき時代のお寺なんでしょう。それぐらい絵との出会いは
ものすごく大きい。絵を見つめて自分を見つめなおす。そういう時間が今、
一番必要なんじゃないでしょうか。>
彼自身、一枚の絵(デューラーの自画像)に出会ったことで、
人生の転機を迎えたという体験があるそうです。
やっぱりそうか!と思いました。
美術でも音楽でも、Artの力には底知れぬものがある。
口で言い表すことのできない、いわゆる「ショック」。
その劇的なる出会いが、人生を変えてしまうことだってあるんです。
出会いは大きい。人との出会いはもちろんだけど、
Artにも、もっともっと出会うべき。
そして、こどもたちには できるだけ先人の
作品を伝えていかなければ。
大人にはそういう使命もあると思いました。
合唱伴奏に合格しました!
Rちゃんの通っている私立小学校では、
毎年秋に、大々的に「音楽発表会」があります。
全学年それぞれに工夫をこらしたプログラムが
組まれ、生徒も保護者の方々も たのしみに
しているイベントのひとつだそう。
Rちゃんは、その音楽会の 2年生の合唱曲の
ピアノ伴奏オーディションに、去年に引き続き
今年も みごと合格したのです。
(ヤッター~!!!\(^o^)/)
なにせ、このRちゃんのオーディションにかける
情熱たるや、ハンパない。(^^;)
1年生だった去年もそうでしたが、自分の実力を
超えるムズかしい曲にも、おじけることなく果敢に挑戦!
いったん「やる!」と決めたら、ひたすら「やる!」
朝から晩まで、オーディションに向けて練習にはげみました。
そして、結果はちゃんと出たのです。
先生は、心の中で舌をまいています。
ほんまにようがんばった。(^_-)-☆
でも、これからが本当の勝負だね。
こまかいところもきちんと演奏できるように努力しよ。
みんなが歌いやすいように、ノリやすいように、
さらに伴奏にみがきをかけていこ!
Rちゃん、心から応援しているよ。(^^)
音楽のテスト97点!
中3のHくんから、うれしい報告がありました。
つい先ごろ行われた期末試験の「音楽」のテストが
97点だったとのこと!\(^o^)/
例によって、試験の前はレッスン時間を
テスト対策にあててきました。
何度も模擬テストをくり返し、書いて、空で暗唱して、答えを確かめて。
地道な努力をコツコツと続けた結果、Hくん自身の「音楽」のテスト史上
最高の点数をとることができたのです。
本当に彼はまじめ。
そして、目標に対してまっしぐらです。
その妥協を許さない態度には、こちらも学ばされるものがあります。
うれしそうなHくんでしたが、もう心は次に向かっているみたい。
だって、彼の目標はあくまで「100点」なんですから。
あと3点めざして、次の期末はさらに頑張るとのことでした。
(オマケですが、100点取ったら教室のごほうびシール
5枚ゲットできるってのもねらってるらしい。(^^;) )
中学のあいだに絶対満点取ろう!
先生は全面的にサポートする。
そして、クラシックの新曲もまた決めてがんばっていこな!(^_-)-☆
「疲れた~」は「がんばった~」
え?めちゃくちゃしんどい?
しんどいだけじゃなくて、イライラのピーク?
おまけに、やらなければいけないことは山積。
あれもこれもそれもどれも、みんなやりかけたままだし、
家の中はちっとも片づかないし。
もしかして、自分はダメだ、ダメだと思っていませんか?
こんだけがんばっているんですもの。
疲れて当たり前。
しんどいの、当たり前。
「疲れた~」は、「がんばった~!!\(^o^)/」にチェンジ。
そして、ちょっとは休みましょう。
堂々と、ね。(^_-)-☆

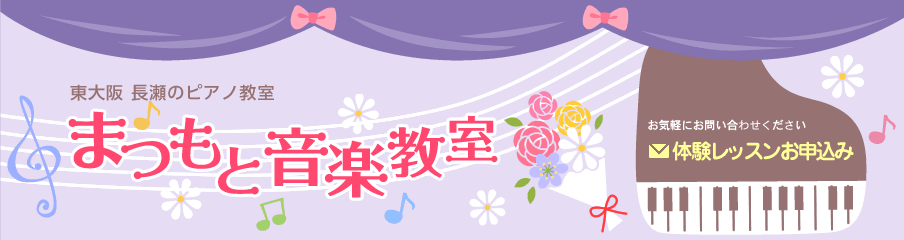
![water-61991_150[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/water-61991_1501.jpg)
![220px-Papageno[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/220px-Papageno1-177x300.jpg)
![image[2]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/image2.jpg)
![5952398269_e3fb18233f_m[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/5952398269_e3fb18233f_m1.jpg)

![D157_winchik20tobira500-thumb-186xauto-2555[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/D157_winchik20tobira500-thumb-186xauto-25551.jpg)
![MKJ_haibisukasunohana500-thumb-260xauto-1241[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/MKJ_haibisukasunohana500-thumb-260xauto-12411.jpg)
![Console[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/Console1-259x300.jpg)
![13-18-03-23_250x250[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/13-18-03-23_250x2501.jpg)
![dog-123722_150[1]](https://matsumoto-music.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/dog-123722_1501.jpg)

